とと姉ちゃん|あなたの暮しのモデルは暮しの手帖!なぜ売れた?
朝ドラ『とと姉ちゃん』は、病死した父親代わりに家長として家族を支えた
小橋常子(高畑充希)の一代記。
常子は後に出版社を立ち上げて、ふたりの妹の鞠子(相良樹)と
美子(杉咲花)もこれに合流します。
そして常子たちが刊行した雑誌が「あなたの暮し」です。
この雑誌のモデルは、大橋鎭子が花森安治とともに出版した
「暮しの手帖」です。
「暮しの手帖」は戦後に大ヒットした雑誌で、現在も発売されており、
根強い人気を誇っています。
この雑誌はなぜ売れたのでしょうか?
大ヒットの秘密に迫ってみました。
コンテンツ
あなたの暮しのモデルは暮しの手帖!なぜ売れた?
スポンサードリンク
昭和21年(1946年)にドラマの小橋常子のモデルとなった大橋鎭子が、
編集者の花森安治とともに衣装研究所という出版社を立ち上げます。
そして昭和23年(1948年)9月に創刊したのが、後の「暮しの手帖」となる
「美しい暮しの手帖」でした。
※それ以前に「スタイルブック」という雑誌を刊行している
この雑誌は、当時としては珍しかった家庭向けの総合雑誌です。
主に主婦層をターゲットにしており、ファッションや食べ物、料理、
医療や健康関係など暮しの衣食住にわたる様々な話題を提供してきました。
当初は家庭向けの総合雑誌自体が珍しかったのですが、
内容も全体的に地味と受け取られたためなかなか売れませんでした。
しかし編集長の花森安治の指揮のもと、良質の内容にこだわった
同誌は様々な企画を生み出して読者の心を掴んでいきます。
「直線裁ち」による洋服の製作、商品テスト、衣食住にまつわる生活の知恵、
豪華な執筆陣によるコラム…などなど
その結果、創刊号はわずか7000部だった売上も、昭和28年(1952年)の
第20号では10万部を突破し、昭和30年(1955年)には20万部を突破。
以降も売上は伸び続け、ピーク時には90万~100万部もの人気雑誌となって
いきます。
スポンサードリンク
そしてそんな暮しの手帖の人気を支えた大きな要因のひとつは、
同誌が外部からの広告を受け付けないというユニークなスタンス。
どのような書籍でも、どうしても広告主には気を使ってしまうことから、
あくまでも中立性を貫くためにこのようなスタンスをとりました。
その結果、同誌の目玉の市販商品の品質や安全性のテスト結果の記事は、
消費者目線からの中立性が保たれて、非常に評判となります。
テスト自体もかなり厳格におこなってきたこともあり、製品メーカーにも
大きな影響を与えることにさえなります。
このような練りに練られた良質の内容や外部の広告を一切受け付けない
スタンス、画期的な商品テストなどの企画によって長きに渡って
読者に愛読される理由となりました。
商品テストの記事は、人手とコストがかかることから残念ながら
平成19年の2月発売号をもって終了しましたが、この雑誌が刊行されたのは
昭和23年ですから、かなり斬新なアイデアでしたね。
当初の季刊から隔月刊に変更はあったものの、良質な生活情報の提供にこだわったので、
月刊や週刊などにはしませんでした。
人気雑誌で発行部数も多かったにも関わらず、あくまでも雑誌の内容にこだわったのは、
創業者の大橋鎭子や花森安治のこだわりでしょうね~
ちょっと売れると、さらなる売上増を目指して姉妹誌などを刊行する
昨今の出版社とは一線を画していたのですね。
このような「暮しの手帖」のスタンスは高く評価され、昭和31年(1956年)には
「婦人家庭雑誌に新しい形式を生み出した努力」を買われて、菊池寛賞も受賞。
菊池寛賞と言えば、文芸・映画などの様々な文化分野で功績をあげた
個人や団体に贈られる賞で、受賞者や受賞団体も錚々たるものですから、
いかにこの雑誌が良質なものであることを示していますね~
現在では消費者モニターや商品の検証などの企画は多くの雑誌でおこなわれていますが、
戦後間もなくこのような企画を実行したアイデアはすごいですね~
またこの雑誌のあくまでも消費者側に立つスタンスを保つため、
外部からの広告を一切断って、中立性を保つ姿勢は共感できます。
とは言え、雑誌の収入源はその売り上げと広告ですから、そのうちのひとつを
自ら断つという決断は並々ならぬ覚悟が必要なことです。
しかもその分は定価に上乗せされるので、同誌はいつの時代も
同種の他社の雑誌より値段が高めというハンデを負っていました。
しかしそれをやり抜いたからこそ、消費者からも支持を得て人気雑誌となりました。
この雑誌の編集長だった花森安治や社主の大橋鎭子らの気概すら感じます。
このようなスタンスで、現在でも多くの読者に愛読されている「暮しの手帖」。
お時間があれば、ぜひご覧になってくださいね!
スポンサードリンク

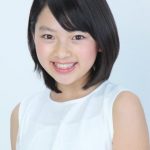








最近のコメント